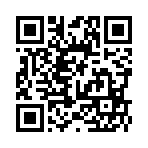2011年06月21日
清水ウォーターフロント条例研究会 誕生!
はじめまして、清水ウォーターフロント条例研究会代表の
HIROTAKAです。
清水ウォーターフロント条例研究会は、静岡市清水区のまちづくりを考える
自主勉強会です。
~富士山の見える理想郷をつくろう!~
を活動テーマに、頑張ります。
よろしくお願いします。
活動の詳細は、下記のとおりです。
<グループ名>
~富士山の見える理想郷~
清水ウォーターフロント条例研究会
<代表者名>
HIROTAKA
<活動テーマ>
清水区のウォーターフロントを日本一住みやすい地区にすることを目的として、
富士山の見える理想郷 清水ウォーターフロント条例の研究をする。
そのために必要な市民参画、市民との情報共有(世論形成)を研究及び実践する。
<活動内容>
下記の研究をする。
・条例づくりのプロセスと市民参画
・過去の災害史から、特に地震、津波の避難を万全にする
・観光と災害に強いまちを共存(電線地中化等の研究)
・新交通
・日の出地区再開発
・JR清水駅から続く清水港線と自転車道・ランニング道を研究することで、「美容と健康」をテーマにする。
・JR清水駅と日の出地区の観光ルート確立(観光客にわかりやすいルートを研究する)
・JR清水駅の東西連携、新文化会館(マリナート)の活用
・県営港から市民港への研究
・清水次郎長の心意気を伝える。「次郎長三国志」を考える
<活動計画>
活動内容を広く伝えるため下記のシンポジウムを企画したい。
・静岡市の合併で目指したものを再考するシンポジウム
・村上元三の次郎長三国志が伝える「心豊かな生き方」を考えるシンポジウム
Posted by HIROTAKA at 23:57│Comments(2)
│清水ウォーターフロント条例研究会とは
この記事へのコメント
巴川に係留している船をどうすべきと思いますか?
係留禁止なのに係留している。
舟の持ち主の意見、考えは知りませんが、市はどうしようと
しているのか?
津波がきて川から波に乗って民家を直撃する恐れが大。
周りの住民はなぜ問題としないのか?
係留禁止なのに係留している。
舟の持ち主の意見、考えは知りませんが、市はどうしようと
しているのか?
津波がきて川から波に乗って民家を直撃する恐れが大。
周りの住民はなぜ問題としないのか?
Posted by SUZUKI at 2011年07月20日 01:33
SUZUKIさん
コメントと貴重な情報、ありがとうございます。
巴川に係留している船、係留禁止なんですか?!(不勉強で、すみません)釣船を生業としているお店もあり、一律禁止ではないのではないかと推測していますが、どうでしょうか?
たしかに、静岡県の港湾計画では、折戸湾などに船を移動してもらいたいようです。一律の移動とは厳しい条件だと思っていましたが、津波などの対策としてということなら説得力があります。
憩える水辺を研究する時、最重要課題は、「安全」だと思います。その意味では、SUZUKIさんの視点を参考にさせて頂き、一層研究していこうと思います。
今後もご意見等、よろしくお願いします。
ちなみに、150年前の安政地震の記録(古文書)では、巴川沿い、たとえば清水町などは、揺れによる潰れ、及び焼失が中心的な被害だったようです。もっとも、三保には大きな津波が来たとの記述が目立ちます。清水町付近の記述でも「津浪向嶋を打ち越し、逆浪にて大船は破損多く、漁船・小舟は押し流され、船具・漁具を失い・・・」との記述もあります。(巴川は地震の隆起により川幅がかなり狭くなったようですから、現在とは地形が少し違ったと思われますので、それを踏まえ今後の参考にすべきと思います。)
東北の震災の津波を見ると、わがまちにも同じ状況を当てはめてしまいそうですが、想定震源域と距離的にとても近い静岡市清水区は、地震後すぐに津波が襲来する可能性がある一方で、津波の高さは、東北の震災のようではないかもしれません(東北震災では、震源と陸地に距離があるため地震後30分以上もたってから大津波が襲来しています。距離が離れるほど津波は大きなものになります。)
起こり得る東海地震では、150年前と地形も、構造物もかなり変わっていますから、危険物もかなり増えている状況です。そうした中でも、これまでの地域震災史や、地質研究の結果を踏まえた正確な情報が、地域の本当の姿を浮き彫りにし、必要な備えをする判断材料となるし、漠然とした不安をあおられるという状況を避けることになるので、行政にはそうした情報提供を期待します。
コメントと貴重な情報、ありがとうございます。
巴川に係留している船、係留禁止なんですか?!(不勉強で、すみません)釣船を生業としているお店もあり、一律禁止ではないのではないかと推測していますが、どうでしょうか?
たしかに、静岡県の港湾計画では、折戸湾などに船を移動してもらいたいようです。一律の移動とは厳しい条件だと思っていましたが、津波などの対策としてということなら説得力があります。
憩える水辺を研究する時、最重要課題は、「安全」だと思います。その意味では、SUZUKIさんの視点を参考にさせて頂き、一層研究していこうと思います。
今後もご意見等、よろしくお願いします。
ちなみに、150年前の安政地震の記録(古文書)では、巴川沿い、たとえば清水町などは、揺れによる潰れ、及び焼失が中心的な被害だったようです。もっとも、三保には大きな津波が来たとの記述が目立ちます。清水町付近の記述でも「津浪向嶋を打ち越し、逆浪にて大船は破損多く、漁船・小舟は押し流され、船具・漁具を失い・・・」との記述もあります。(巴川は地震の隆起により川幅がかなり狭くなったようですから、現在とは地形が少し違ったと思われますので、それを踏まえ今後の参考にすべきと思います。)
東北の震災の津波を見ると、わがまちにも同じ状況を当てはめてしまいそうですが、想定震源域と距離的にとても近い静岡市清水区は、地震後すぐに津波が襲来する可能性がある一方で、津波の高さは、東北の震災のようではないかもしれません(東北震災では、震源と陸地に距離があるため地震後30分以上もたってから大津波が襲来しています。距離が離れるほど津波は大きなものになります。)
起こり得る東海地震では、150年前と地形も、構造物もかなり変わっていますから、危険物もかなり増えている状況です。そうした中でも、これまでの地域震災史や、地質研究の結果を踏まえた正確な情報が、地域の本当の姿を浮き彫りにし、必要な備えをする判断材料となるし、漠然とした不安をあおられるという状況を避けることになるので、行政にはそうした情報提供を期待します。
Posted by HIROTAKA at 2011年07月26日 23:47
at 2011年07月26日 23:47
 at 2011年07月26日 23:47
at 2011年07月26日 23:47